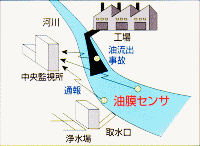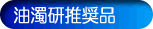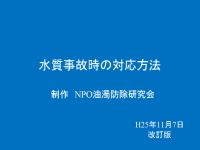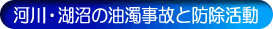
油や有害液体物質による水質事故が発生したら・・・・
水質担当者が直面する課題を
(1)予防活動 (2)防除活動の手順 (3)具体例(画像・動画)
に分類して、国、都道府県で実施致しました資料を基に講習用データにまとめました。
→河川・湖沼の油濁事故と防除活動(PDF)
|
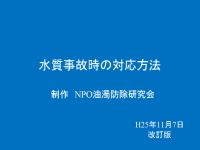 |
|
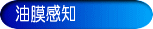
河川と海とでは事故の様相が大きく異なります。海洋では、界面活性剤で油を拡散し自然浄化を待つ持久戦が可能です。しかし河川
では流れがあり、地域住民の生活が直近に存する事から、被害の拡がりが速く、初動対応の迅速性が要求されます。油の漏洩を早期
感知できれば、処理作業全般に渡る費用は、大幅に軽減されます。浮遊式やレーザー反射式ののセンサでは、極めて薄い油膜を昼夜問わずに監視し
、警報、緊急バルブ停止等の移信号を発します。
|
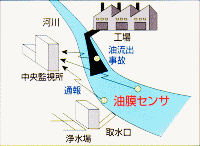 |
|
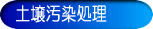
汚染された土壌から油や有害液体物質を除去する場合、大掛かりな土木工事による土の置換をする必要が生じますが、建物が障害にな
ったり廃土処理が問題になるケースが多いようです。(写真1)のように仮設井戸へ油類を誘導し遠心分離機で油分だけを回収する方法
により、水位で移動する汚染部分を着実に浄化できます。このとき、地下水は分離槽を通じて土壌に戻るので、地盤沈下の心配はあり
ません。緊急時の処理方法として、掘削して、粉末油ゲル化剤で固化、蒸発抑制する方法や土壌改良剤を散布するなどの方法も併用します。
|

写真1
|

|

|

|
|
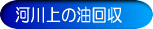
従来から、オイルフェンスの展張で油の拡散を止め、フェンス上流の水面で吸着マットを使用して回収する方法が採用 されています。当会では、人工河川を使用した油吸着実験のデータから、毎秒3mの流速でも、従来型吸着マットでは著
しく性能低下する事を確認し、河川用粉末油ゲル化剤や河川用吸着マットを紹介しています。河川用粉末油ゲル化剤は 、厚い油層も薄い油膜にも対応し、特に蒸発抑制効果が大きく、流れのある油膜回収にも効果を発揮します。
|
|

センシティビィティマップとは、環境脆弱性指標図を意味する特殊情報図です。河川の事故では、地形や動植物の生態系 などの条件により千差万別の対応が求められます。河川毎の事故シュミレーションを事前に想定し防除活動の情報を関係
者が共有するため、このMapを提案します。
防除活動の基本は、事前の「防除計画」の作成です。防除計画の作成支援も、当会の重要な事案のひとつです。
|
|
|
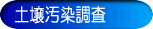
河川の油流出事故では、流域事業所の土壌汚染が気温の上昇や地下水位の変動にともなって湧出するケースが多く見受けられます。
しかし、地中に広がる目に見えない土壌汚染の位置や深さを特定することは困難で大変な作業でした。この問題を解決したのが、地
中レーダーを利用した土壌汚染調査です。孔開けや掘削をおこなわずに地表面からの非破壊調査で、地中の汚染を立体的な面の解析
画像で捉えます。スポット情報で高価なコアボーリング情報と比べて、正確な修復対策の立案が可能です。ボーリングが困 難な操業中の工場でも、2〜3日間の非破壊調査で測定可能です。(解析には5〜10日間必要です)
|

地下の汚染を土壌レーダーで調査
|
|
|
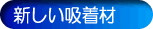
現在多く使用されている化学繊維を用いた吸着材に加え、天然素材(ピートモス、間伐材、炭、黒曜石etc)を利用したものが開発されています。
事故の様相は色々なケースがあり、その場面に適した防資材を選択する事が必要です。
 |
 |
 |
 |
間伐材を利用したもの |
黒曜石を利用したもの |
ピートモスを利用したもの |
PP製吹流し材 |
|
|
|
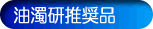
事故現場からの要請で開発した以下の2点を推奨品としております。
飛び丸

|
油膜用吹流し材αNZ-1

|
投げ込み型の吸着マットで、油ゲル化剤を封入しています。水に沈まず、油膜の挙動と同方向に移動します。
国土交通省との共同作業です。 |
流出油膜を止めるのではなく、流れの中で吸着する事をコンセプトにしたものです。 |
|
|